停止処分者講習(免停講習)は免停が決まった人に該当する講習。講習を受けることで点数に応じて免停期間を短縮することができます。
ただ停止処分者講習については何となくでわかっても、実際に講習を受けた事がないと必要なものや講習の流れが今いちわからないという方も少なくないですよね。

そこでこの記事では、停止処分者講習の手順について一連の流れをまとめてみました。
停止処分者講習は強制ではないが…

停止処分者講習は強制ではないので、必ず受けなければいけないという訳ではありません。あくまで免停になった人向けに講習がありますよという事。
仮に受けないからと言ってペナルティが課されることもありません。免許停止日数が短縮されないだけ。
受講することで免停期間が短縮できる
逆に停止処分者講習を受けて不可以外の優・良・可いずれかになれば短縮ができます。
| 優 | 短縮日数:29日 停止日数:1日 |
| 良 | 短縮日数:25日 停止日数:5日 |
| 可 | 短縮日数:20日 停止日数:10日 |
| 不可 | 短縮日数:0日 停止日数:30日 |

中でも優に該当すれば29日短縮の1日で免停期間が済みます。
ただし受けるためには事前予約が必要
ただし停止処分者講習はその日に行ってそのまま受けられる訳でなく、事前に予約を済ませる必要があります。
祝日・休日・年末年始を除いた平日に
予約を入れて講習を受講しましょう。
停止処分者講習(免停講習)に必要な持ち物

筆記用具
受講料
眼鏡等
行政処分呼出通知書
行政処分呼出通知書は呼出通知書とも呼ばれるもの。
免許停止処分の人に警察から送られる書類です。一般的には事故から数週間~1か月程度で送られることがほとんど。

もし通知書が届かない場合は、【行政処分呼出通知書(免停通知)が届かない原因2つと解決策】で解決策をまとめているので参考にしてみてください。
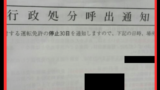
筆記用具
・シャーペン
・消しゴム
マークシートを塗りつぶす作業があるので、鉛筆やシャーペンなどがあればOKです。
逆にボールペンは使用できないので注意。
※もし当日忘れた方は販売店で50円程で購入ができます。
受講料
受講料は免停日数(短期・中期・長期)いずれかで代わります。
・中期(60日)19,500円
・長期(90日以上)23,400円
当然免停日数が多ければその分費用も大きく変わります。
眼鏡等
眼鏡等は免許に記載がある人だけ。裸眼でも
問題ない人は準備する必要はありません。
スポンサーリンク
実際の停止処分者講習(免停講習)の流れ

ここからは実際の停止処分者講習の流れ
についてお伝えしていきます。
オリエンテーションやペーパー検査
教本講義(座学)①
機械検査・CRT運転適性診断
教本講義(座学)②
考査(マークシート方式)
安全度・事故原因考察
運転シミュレーター
講習終了証明書交付
講習終了証明書と引き換えに免許証を受け取る
受付で手続きをする
まず受付にて必要な手続きをしましょう。分室窓口で必要な手続きと一緒に運転免許を預けます。
オリエンテーションやペーパー検査
オリエンテーションは、講習の内容や評価基準等について説明をします。評価は講習態度や考査の点数を元に採点。
ペーパー検査については運転適性検査を行います。検査の結果自体は評価に関係しませんが、講習態度の対象にはなるので注意。
教本講義(座学)①
全日本交通安全協会が発行する教本を
元に1時間ほど講義を受けます。
内容は主に
・交通事故を起こした際の責任問題など
交通ルールに関することを学びます。
※居眠り等をしてしまうと状況に応じて減点の対象になるので注意が必要。
機械検査・CRT運転適性診断
5分ほど休憩をはさんだ後に機械による検査をします。機械の運転適正審査は、視力測定・動体視力・視覚刺激反応・夜間視力等を確認。運転前の視力に関する検査。
CRT運転適性診断はハンドルやペダルを操作して行う機械を使った診断の事。反応速度や操作性・注意力を検査します。
教本講義(座学)②
60分ほど昼休みをはさんだ後に残りの教本講義(座学)を学びます。
午前中にやった講義の続き。一時間を使って残りの内容を把握します。
考査(マークシート方式)
考査はマークシートによる筆記テスト。問題は40問出題されて、36点以上で停止期間が29日短縮となります。
※点数によって優・良・可・不可の4種類。
| 優 | 短縮日数:29日 停止日数:1日 |
| 良 | 短縮日数:25日 停止日数:5日 |
| 可 | 短縮日数:20日 停止日数:10日 |
| 不可 | 短縮日数:0日 停止日数:30日 |
安全度・事故原因考察
安全度・事故原因考察はペーパー検査の
運転適性検査の内容を元に悪い点を指摘されます。
また、安全運転のしおりを用いて免許の点数制度や違反など。安全運転に関する内容を再認識します。
運転シミュレーター
シミュレーター(模擬運転検査)は
・見通しが悪い道路の通過
・一時停止が必要な交差点の通過など
事故が起こりやすいケースを元にシミュレーター(模擬運転検査)にて操作しながら学びます。
※成績に影響はありませんが、悪意のある態度を続けると講習の評価対象になるので注意。
講習終了証明書交付
一連の講習が終了したら最後に講習終了証明書を受け取ります。講習終了証明書は講習態度と考査が成績によりまとめられたもの。
この結果で【優】がでれば29日短縮の1日で免停期間が終了します。
講習終了証明書と引き換えに免許証を受け取る
あとは講習終了証明書と引き換えに免許証を受け取るだけ。初めの受付で手続きした場所(分室窓口)で免許証を変換してもらいましょう。
一連の流れをまとめると
オリエンテーションやペーパー検査 9:15~
教本講義(座学)① 9:55~
5分休憩
機械検査・CRT運転適性診断 11:00~
昼休み 12:00~
教本講義(座学)② 13:00~
5分休憩
考査(マークシート方式)14:00~
安全度・事故原因考察 14:35~
運転シミュレーター 15:15~
講習終了証明書と引き換えに免許証を受け取る 16:15
解散 16:20
記事のまとめ
以上、停止処分者講習(免停講習)に必要な持ち物や当日の講習の流れをお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
筆記用具
受講料
眼鏡等
オリエンテーションやペーパー検査
教本講義(座学)①
機械検査・CRT運転適性診断
教本講義(座学)②
考査(マークシート方式)
安全度・事故原因考察
運転シミュレーター
講習終了証明書交付
講習終了証明書と引き換えに免許証を受け取る
停止処分者講習は強制の講習ではないものの、受講することで採点に応じて免停期間を短縮できます。
| 優 | 短縮日数:29日 停止日数:1日 |
| 良 | 短縮日数:25日 停止日数:5日 |
| 可 | 短縮日数:20日 停止日数:10日 |
| 不可 | 短縮日数:0日 停止日数:30日 |

問題は40問出題されて36点以上で停止期間が29日短縮(1日)となるので、もし受講する場合には優を目指して講習を受けてみましょう。
に-必要な持ち物や当日の講習の流れ-1.png)